
©︎ 2021-2026 DEAP Inc.
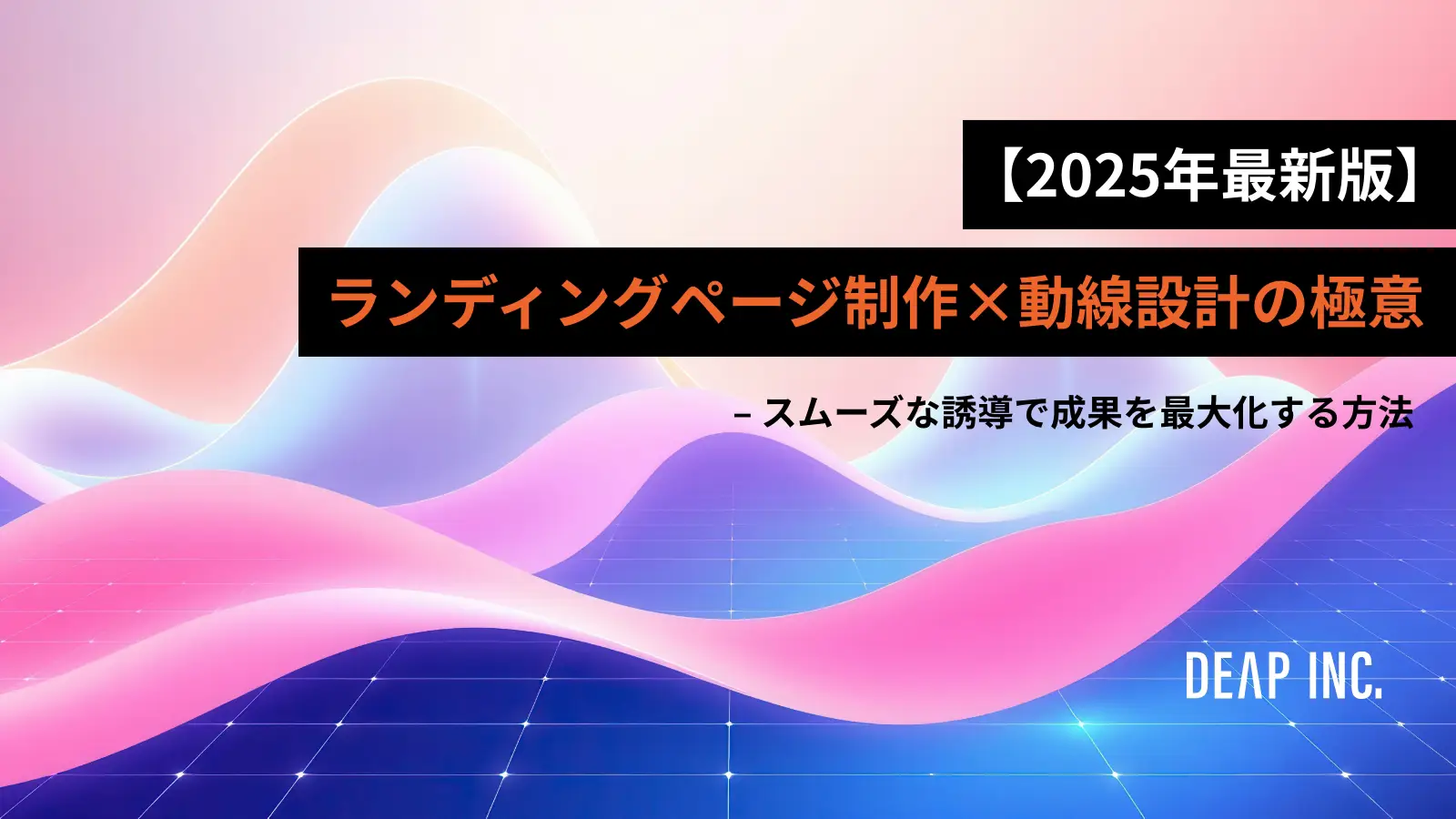
ランディングページ(以下、LP)は、企業やサービスが抱える課題を解決したり、商品・サービスの成約率を高めたりするための極めて重要なツールです。近年ではSNSや広告など、多彩なチャネルからLPへ誘導するケースが増えており、訪問者をいかにスムーズに目的地点(問い合わせ、資料請求、購入など)へ導けるかが成功のカギを握っています。そこで重要になるのが「動線設計」です。
本記事では、LP制作をさらに効果的にする動線設計のポイントや実践的なステップ、計測と改善の方法まで、10,000文字をかけて徹底的に解説します。実際の運用にすぐ活かせる知識をまとめていますので、ぜひ最後までご覧いただき、御社のビジネス成果の最大化にお役立てください。
目次
ランディングページにおける動線設計とは、訪問者がLPに訪れてから最終的な目的(例:問い合わせ、商品の購入、会員登録など)に到達するまでの経路を事前にデザインし、最適化することを指します。広告のクリエイティブや、SNS投稿の内容、オウンドメディアの記事からLPへ誘導するケースなど、LPに流入する入口は多岐にわたります。しかし、流入後に訪問者が次の行動をスムーズに取れなければ、高い離脱率・低いコンバージョン率につながります。これを避けるには、ユーザーの行動心理や視線の動き、ページ内誘導の要素を熟知する必要があります。

ユーザーにとってわかりやすくスムーズな導線は、余計なストレスを与えません。結果として、目的の行動(購入・問い合わせなど)を起こしやすくなり、コンバージョン率が上がります。
必要な情報が見つからない、どこをクリックすれば問い合わせフォームへ行けるのかわからない、などの状態があるとユーザーはすぐに離脱してしまいます。動線設計をしっかり行うことで、離脱要因を最小限に抑えることができます。
せっかく広告を出しても、LPの動線が悪いと広告費の投資対効果(ROI)が悪化します。また、LPの内容を十分に検討せずに作り直しを繰り返すと制作コストや運用コストも増大します。最初にしっかり設計しておくことで、広告費や制作費のムダを減らすことができます。

動線設計を行う前提として、ターゲットのペルソナ設定が重要です。例えば、以下のような項目を明確にしておくと設計がしやすくなります。
ペルソナを具体的にイメージしながら動線を組み立てると、ユーザーが抱える疑問や不安を解消しながらスムーズにゴールへ誘導できる設計が可能になります。
LPの動線設計を成功させるためには、ページ全体を俯瞰したうえで主要要素を的確に配置し、ユーザーの目線や意識の流れをコントロールする必要があります。以下に、特に重要なポイントをピックアップして解説します。
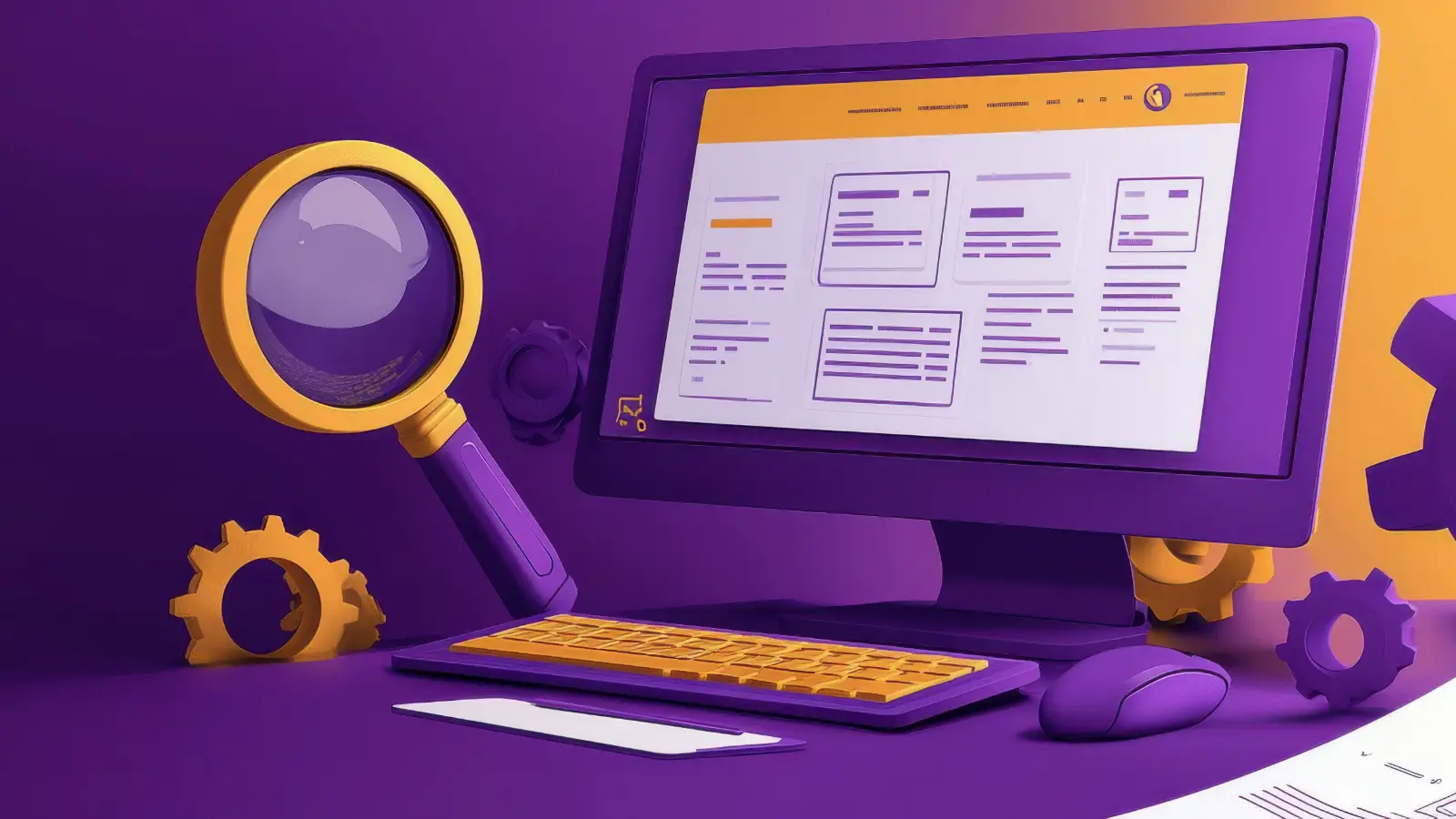
ユーザーが最初に目にする見出しは、一目で興味やメリットが伝わるように工夫します。
メインビジュアルやイメージ画像、CTAボタン(問い合わせや購入ボタンなど)を視線の流れに沿って配置すると効果的です。
ファーストビューで「興味を持ったユーザーが次に取るアクション」を明確化しておくと離脱を防げます。

単に商品やサービスの特長を羅列するだけではユーザーの心は動きません。興味を引くためのストーリー性を加えながら、段階的に理解を深めてもらうことが重要です。
H2やH3などの見出しを体系的に設定し、各段階ごとに伝えたい内容を整理します。
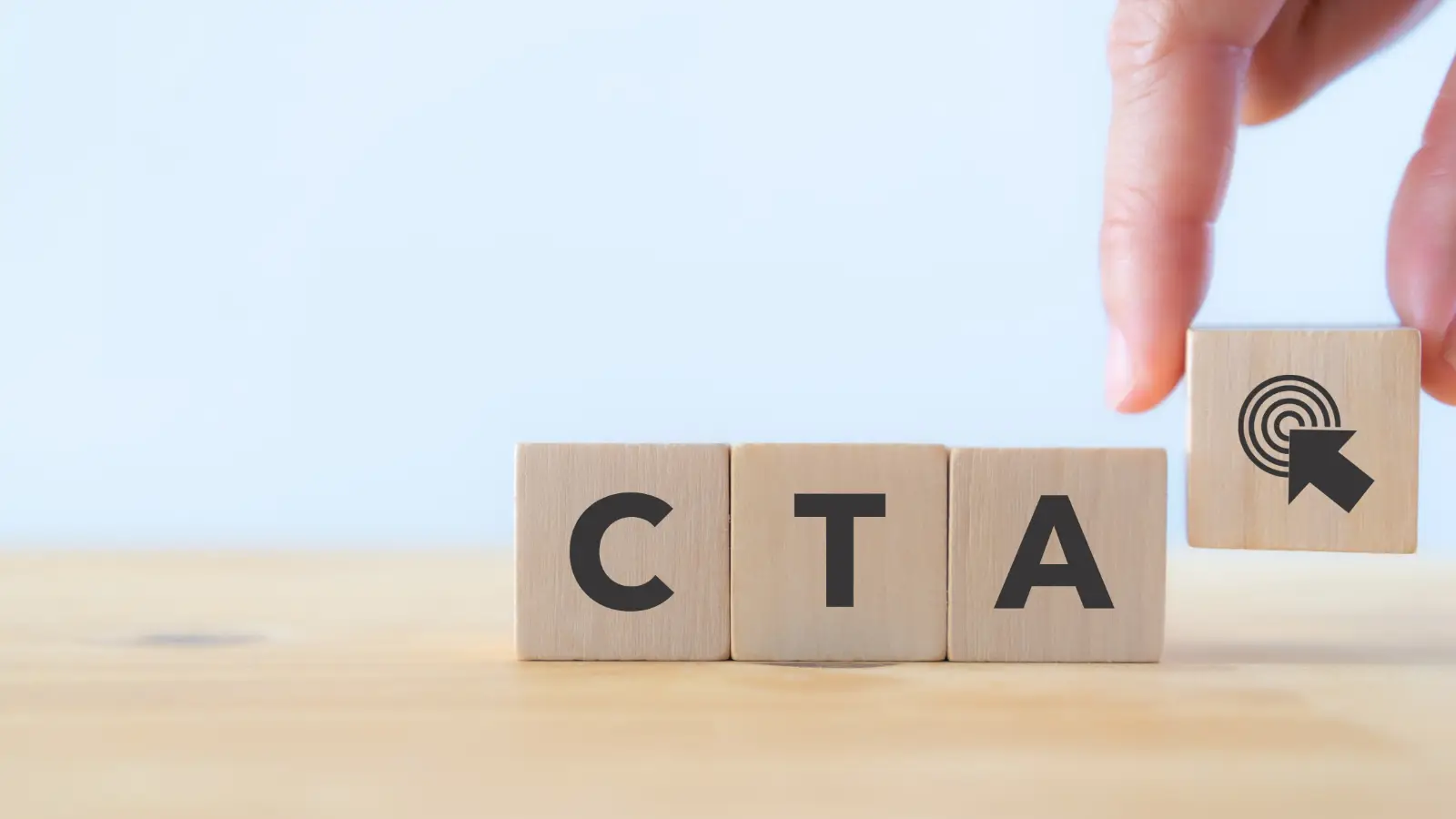
CTAボタンは目立つ色を使い、画面をスクロールしても常に見える位置(固定配置)にするか、各セクションごとに必ず配置する方法が効果的です。
「資料請求はこちら」や「問い合わせる」「無料で相談する」など、ユーザーが行動するメリットが伝わる言葉を使います。
LPが長い場合、1ページ内に複数のCTAを設置することで、ユーザーが興味を持ったタイミングですぐに行動できるようにします。

真実にもとづいた実績や顧客レビュー、SNSでの高評価などを適切に紹介します。数字や具体的データがあると信頼度が高まります。
権威ある機関の認証や、著名人からの推薦など、実在する形でのエビデンスがあると強い説得力を持ちます。架空の話はNGですので、実在の実績だけを示しましょう。

ユーザーが抱える疑問や不安を先回りして解消できるように、Q&Aを充実させます。
ページ下部にもCTAを置き、ユーザーが最後に「どう行動すればよいのか」を再提示するとコンバージョン率が高まります。
LPの動線設計は「計画→実装→運用・改善」という流れで継続的に行うことが理想です。ここでは、具体的なステップについて詳述します。
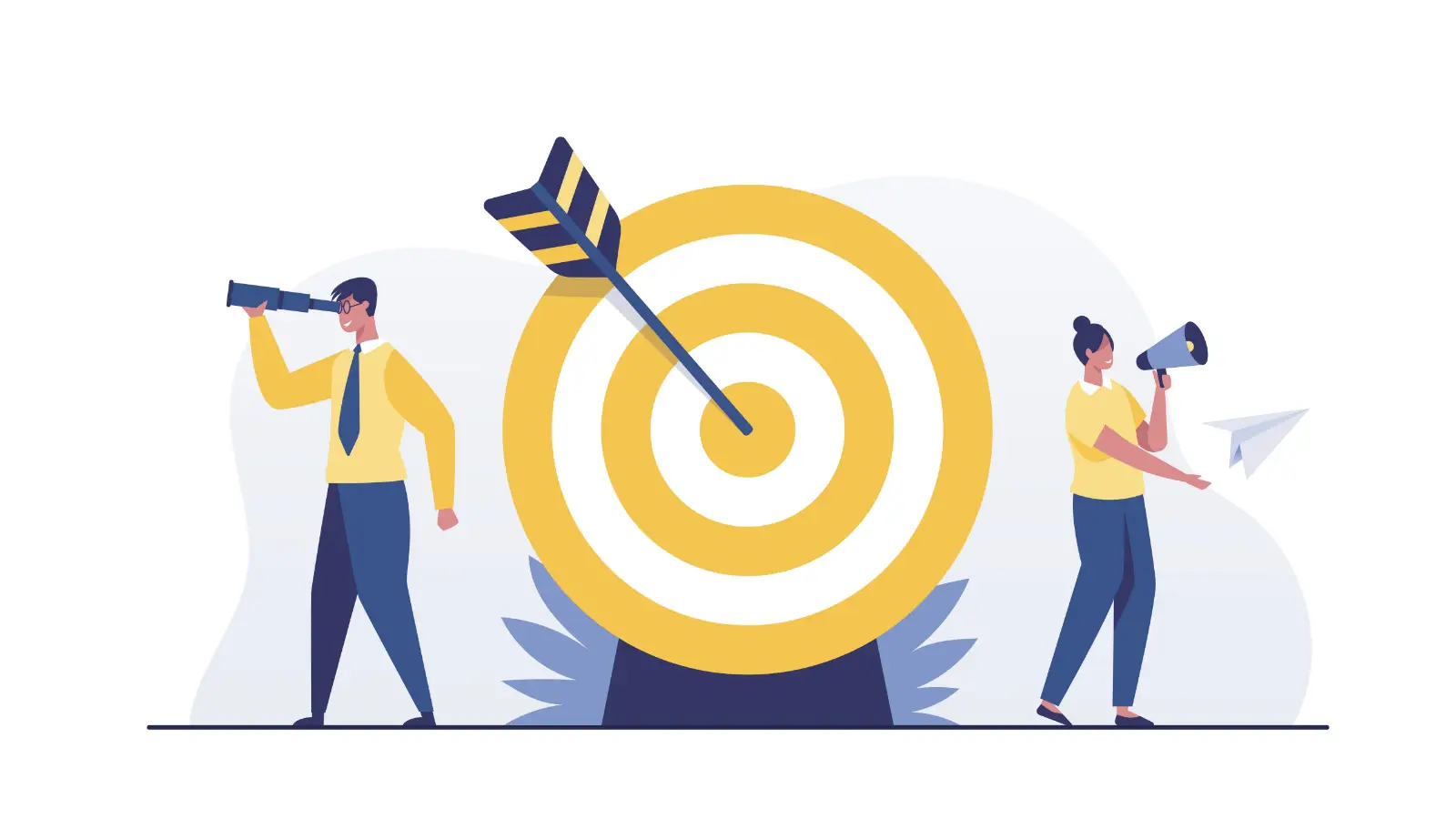
商品販売、メールアドレス獲得、セミナー申し込みなど、LPのゴールを明確にします。
前述したペルソナを策定し、どのような行動フローが理想かをイメージします。

冒頭で興味を引く→商品・サービス概要→メリットや差別化点→証拠(ソーシャルプルーフ)→CTAといった流れを紙やスプレッドシートなどで簡単に整理します。
テキストのボリュームや画像・動画の配置場所を大まかにレイアウトしておきます。

カラー、フォント、余白(ホワイトスペース)を意識し、ユーザーが視線を自然に誘導されるようにします。
読み進めるうちに疑問や不安が解消されていくストーリー構成と、行動を後押しする強いCTA文言を用意します。

LPの各要素(ボタンなど)にクリック計測のタグを仕込み、どこでユーザーが離脱するかを把握します。
ユーザーがページ内のどこを見ているのか、どこでスクロールが止まるのかを視覚的に把握し、改善に役立てます。

CTAの色や位置、テキストを変えるなど、小さなA/Bテストを繰り返し行い、成果を最大化します。
数値だけでなく、ユーザーからの問い合わせ内容、SNSでの反応なども踏まえて総合的に改善します。
LPの効果を最大化するためには、制作・公開して終わりではなく、継続的な計測と改善を行うことが欠かせません。以下、代表的な計測指標と改善アプローチを紹介します。

LP訪問者のうち、実際に目的の行動を取った割合です。これが最も重要な指標の一つです。
LP内のCTAボタンがどの程度クリックされているかを測定します。CTAの配置やデザイン、文言を検討する指標となります。
ページを開いてすぐに離脱するユーザーが多い場合、ファーストビューの設計やコンテンツの質を見直す必要があります。
ページ下部まで読んでいるユーザーがどの程度いるか確認し、CTAの位置やページの長さ、構成を再考する材料とします。

ボタンの位置や色、フォントサイズ、行間を含むレイアウト面の調整を行い、視線の流れを整理します。
ユーザー心理に合わせた訴求ができているか。専門用語ばかりでわかりづらくないか。ターゲットの悩みや目的を的確に捉えた表現を使えているか確認しましょう。
○ボタンの文言を「無料相談する」から「無料で問い合わせる」に変えた場合、クリック率はどう変化するか ○キャッチコピーを変えた場合、CVRはどう変化するか といった定量的な検証を繰り返します。
計測ツールやヒートマップでユーザーが離脱するセクションを把握し、そのセクションの情報不足や説得力の欠如を補う情報を加えるなどの対策を実施します。
2025年現在、LPの動線設計においてはよりユーザーの体験を重視する流れが加速しています。以下では最新のトレンドとポイントを解説します。

スマートフォン利用率がさらに高まる中、モバイルでの読みやすさ・操作しやすさの重要性が増しています。特にモバイル端末でのスクロールがしやすいように、要素の配置を単純化し、CTAボタンを親指操作で届きやすい位置に設置するなどの工夫が不可欠です。

近年、ホバーやスクロールに合わせて変化するアニメーションなど、小さなインタラクションデザインがユーザーの興味を引き、ページ離脱を防ぐテクニックとして注目を集めています。例えば、視線誘導に沿って要素がフェードインする、マイクロアニメーションでCTAボタンを強調するといった手法は、動線設計の一部として活用されます。

ユーザーの属性や行動履歴に基づいてLPの内容を出し分けるパーソナライズも、効果的な動線設計と深く関連しています。広告経由で来たユーザーには広告内容に即した訴求、既存顧客には追加サービスやアップセルを提案するなど、個別最適化を図ることでよりスムーズな誘導が可能になります。

音声検索や音声アシスタントが普及しつつあるなかで、LP自体に音声ガイダンスを導入する企業も一部では見受けられます。すべてのユーザーが対象というわけではありませんが、視覚に加えて聴覚からも動線をサポートする試みとして今後注目される可能性があります。

個人情報保護やクッキー規制強化など、ウェブ上のデータ取扱いに関するルールが世界的に見直されています。ユーザーの同意取得やプライバシーに対する配慮は、動線設計にも影響を与えます。不必要に情報を求めるフォームは離脱の原因になりやすいので、必要最小限の情報取得に留める、取得理由やメリットを明記するなどの工夫が求められます。
LPの動線設計を進めるにあたり、見落としがちな注意点や、最終的に必ず確認しておくべきチェック項目をまとめました。

BtoC領域であれば、テクニカルな用語の使いすぎはユーザーの離脱要因になりやすいです。難しい専門用語が必要な場合は、すぐ近くにわかりやすい補足説明を入れるなどの配慮が必要です。
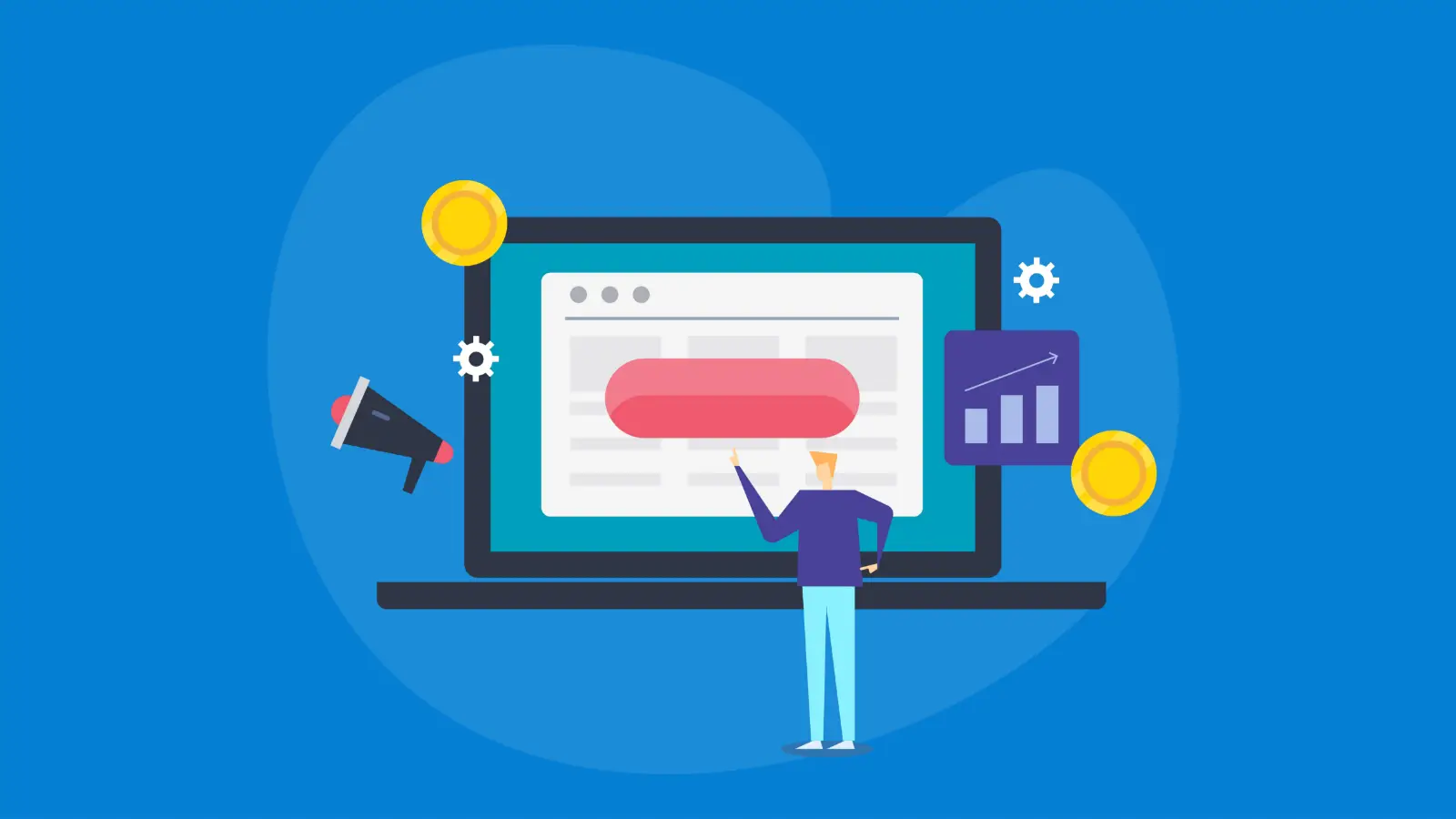
CTAボタンをクリックした後のページが404エラーになる、メールフォームへのリンクが誤っているなど、技術的な不備は信頼を損なう大きな原因になります。公開前に全リンク・フォームテストを必ず行いましょう。

LPで伝えたいことが多すぎる場合、情報を詰め込みすぎると逆に伝わりにくくなります。優先順位をつけて情報を整理し、冗長な部分は削ることが大切です。どうしても詳細情報を掲載する必要があるなら、別ページへのリンクやタブ切り替え表示などで対応しましょう。

動線設計は、PCとスマートフォン、タブレットそれぞれでレイアウトが変わります。特にスマートフォンを中心にデザインを考えることで、ユーザーが迷わない配置にする必要があります。デバイスごとのUI配置チェックを怠らないようにしましょう。

LPは作って終わりではなく、広告やSNSなどの運用とセットで効果を発揮します。定期的にアクセス解析を行い、必要に応じてアップデートできる運用体制を整えておくことが大切です。
最も効果が期待できるのはCTAの改善です。クリック率を高めるためにボタンの色、文言、配置などをA/Bテストで検証してみてください。改善の余地が大きいパートなので、比較的少ない労力で大きな成果を得やすいです。
レスポンシブデザインはモバイルを主体として考える場合でも、PC表示が雑になるわけではありません。モバイルとPCで配置を最適化しつつ同じ情報価値を提供できるように設計するのが望ましいです。近年はモバイルアクセスが大半を占めることもあり、まずはスマホ最適化を優先しながらPCでも整合性を保つのが主流です。
ヒートマップやA/Bテストができるツールは大いに役立ちます。Googleオプティマイズ(2023年9月末でサービス終了済み)やGoogleタグマネージャー、または有料のヒートマップツールを使うことで、ユーザーの行動データを正確に把握し、改善に活かせます。自社の予算や目的に合わせて導入を検討してください。
個人情報保護法や特定商取引法など、入力フォームや商品販売に関わる法律は必ずチェックが必要です。2023年以降はクッキーの同意取得などのプライバシーに関わる規制が国内外ともに強化されています。不必要な情報を取得しない、利用目的を明確に記載するなどの点を徹底しましょう。
情報が過剰でまとまりにくい場合は、ステップ別のページに分けるか、ユーザーが見たい情報だけをすぐに表示できるタブやアコーディオンメニューを使う方法もあります。1ページ完結型が望ましいときは、見出しの構成をしっかり整理し、不要な情報を削ることを検討しましょう。
ペルソナ設定や商品・サービスの強みの明確化、実績データの用意などは自社で行っておくとスムーズです。外部制作会社やデザイナーは、それらをもとに動線設計やデザインを形にしていきます。事前に内容が固まっていないと、制作過程で方向性がぶれたり追加料金が発生する恐れがあるので注意しましょう。
ランディングページ制作における動線設計は、訪問者が抱える課題や欲求を的確に把握し、最短ルートでゴールへ導くための重要なプロセスです。ファーストビューの設計から情報の階層化、CTAの配置、検証ツールを用いた分析・改善に至るまでの一連の流れをしっかり押さえることで、LPのコンバージョン率は大きく向上します。
2025年現在、モバイルファーストやパーソナライズ、ヒートマップなどの技術を活用した実践が進んでおり、今後ますますその重要性が高まっていくでしょう。実際のデータやユーザーの声をもとに検証・改良を繰り返すことで、LPの成果を最大化し、御社のビジネスを加速させる一助となります。
ブランディングプランナーがお話をうかがいます。
まずはお気軽にご相談ください。
電話でのお問い合わせはこちら
受付時間:平日10時〜19時